「曹洞禅ネット」20周年特別座談会(前編)
公式サイト「曹洞禅ネット」20周年特別座談会(前編)
平成28年11月22日、「曹洞禅ネット」の開設20周年を記念した特別座談会が、曹洞宗宗務庁にて開催されました。
「曹洞禅ネット」の事業に係ってきた方々をお招きし、開設から今に至るまでの苦労話や思い出から、今後の事業への期待まで、大変有意義なお話を伺いました。以下に、その内容を報告いたします。
【参加者】
晴山俊英(さん)駒澤大学教授
松尾徹裕(さん)滋賀県願成寺住職(元宗務庁課長)
大森篤史(さん)埼玉県東榮寺住職(広報委員会委員)
三村成信(さん)宗務庁事務員
(司会進行 関根隆紀 人事部文書課課長)

司会:曹洞宗の公式サイトである「曹洞禅ネット」は、今年の12月で開設から20年を迎えることとなりました。
『曹洞宗宗勢のあゆみⅡ』(宗務庁刊)によれば、1996(平成8)年3月11日に、「インターネット開発準備委員会」が開催され、12月には曹洞宗総合研究センターの前身である曹洞宗現代教学研究センターの「曹洞禅ネット推進プロジェクト会議」が中心となり、教学部所管として「曹洞禅ネット」の運営がスタートしました。
1996年といえば「Yahoo!Japan」がサービスを開始した年です。それから20年、IT技術の進歩はすさまじいものがありました。現在「曹洞禅ネット」は1日3000件を超えるアクセスをいただくまでになっています。
多くの方がたのご理解とご協力により、「曹洞禅ネット」を20年間続けることが出来ました。そこで本日はこの20年間を振りかえるとともに、「曹洞禅ネット」の未来を語っていただきたく、座談会を開催いたしました。どうぞ忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。
●開設までのいきさつ
司会:最初に開設までのいきさつや、当初の開設目的などをお伺いしたいと思います。

晴山:「曹洞禅ネット」をスタートする以前、まだパソコン通信の時代に、全曹青(全国曹洞宗青年会)ではネットワークを作ろうという話になりました。たしかウィンドウズ95が出てからインターネット通信が急激に広がったと思いますから、その前の話です。ウィンドウズ3.1を使い、パソコン通信ではニフティやPC-VANを利用していた頃です。
全曹青では、一番最初に僕に話がきまして、一応箱を作ろうという話になりました。その頃、当時は面識がなかった大森さんが全曹青に「これからはインターネットです」とアピールされていました。そこで私は「よし、じゃあ仲間になろう」と、お誘いをして一緒に作業をやり始めました。新しい分野でしたので、作っていく過程において問題はありました。けれども、「青年会」だから冒険してもいいのではないかと、強引に進めていった記憶があります。
司会:もともとのスタートは全曹青の方が早かったということですね。
晴山:早かったですね。全曹青では関係者が集まった折に、その時もこの場所で、僕と大森さん達でデモンストレーションをして、こういうことをやってもよいかという了解をもらった覚えがあります。全曹青はそれで、ひとつの形が出来ていきました。
全曹青でのこの実績から、私は現代教学研究センターの方から声をかけていただき、僕と今、苫小牧駒澤大学にいる星俊道師が、現代教学研究センターで協力することとなりました。
司会:資料では平成8年の3月に「インターネット開発準備委員会」というものが開催されたとありますが、これは宗務庁が主導で行われたのでしょうか。
晴山:これは現代教学研究センターの中でスタートして、現代教学の方から宗務庁に働きかけたのではないでしょうか。現代教学研究センターも、「現代」に対して何ができるか、ということを強調したいという思いがあったと思います。
司会:その働きかけをうけて、宗務庁が「これだったらやろう」といって、曹洞宗としてホームページを正式に設置するという経緯にいたったのですね。
晴山:実際に始めてからは、最初はアクセスカウンターをつけました。
「今日何人見に来たかな」とチェックすると、1件アクセスがある。うれしいのもつかの間、「あ、これ自分のカウントだった」というような調子で始まっていきました。最初はそうやって「動くかどうか」のテストから始めていきました。
司会:まだ一般にはインターネットが見られるような環境はほとんどありませんでした。インターネット利用率は平成8年当時が3%ぐらい、現在は80%を超えています。当時はパソコンすら普及していない時代だと思います。そういう時に、先駆的な企画を立てられたというのは、皆さんには先見の明があったということだと思います。
晴山:ちょうどタイミング的に僕や星さんや大森さんがいて、全曹青というモデルとなるインターネット事業が直前にありましたから。

大森:その頃はプロジェクトには入っていませんでしたが、いつも晴山さんと一緒にいて、色々な経緯を私も横で聞いていました。思い出してみると、全曹青で色々と企画を立てても、実際に実現できる数には限界がありました。そういうこともあり、「曹洞宗のホームページは何を目指すのか」ということを大事にしていたようです。その当時は、学術的な裏付けのあるものを出せるのは「曹洞禅ネット」でないと無理だということで、そういうものをやっていこう。そういう目標が最初にあったのです。
だからこそ、教化施策「グリーンプラン」の調査資料を出したりしました。最初からその辺りは考えていました。また、そのころのQ&Aにオウム真理教に関する記述がありますが、それはパブリックな声明に相当する内容なので、全曹青では出せないものでした。
晴山:やっていく中で、「対象者」をどうしようかという点で、意見が分かれることがありました。少し運営してからまずは「一般の人」に向けたものを目指すようになりました。
司会:「教化活動」という目的が当初からあったのですね。
晴山:たしかに教化活動はしたいけれど、まだ十分なコンテンツがありませんでした。
当時はマンガの掲載をしましたが、ネット掲載をすると本が売れなくなる懸念があり、すでに連載が終わっているものや、廃版になったビデオとかを取り込んで、ネットにアップしていました。それが、どこかのお寺で「子どもたちにパソコンで見せてあげたら喜んだ」といって、御礼のメールをいただいたりすると、それだけで「良かった」と思えました。
開設当初から、漫画や映像ビデオ、あるいは速報などをいち早く出したい、コンテンツを新しくしたい、という構想はありましたが、中々実現は難しかったです。
大森:運営に関しては、その当時は、本部会として宗務庁職員が参加するのが「曹洞禅ネット編集会議」で、現代教学研究センターの研究者が中心となり月1~2回のペースで行う「曹洞禅ネットプロジェクト会議」というのが作業部会でした。その後、現代教学研究センターと宗学研究所と教化研修所が統合され、曹洞宗総合研究センター(以下:総研)になり、総研を挙げて「曹洞禅ネット」と関わる体制になっていきました。
晴山:総研になる以前、まだ部門が分かれていた時代でも、唯一この「曹洞禅ネット」の会議の場だけが、現代教学研究センター、宗学研究所、教化研修所がしっかりと手を取ってチームになっていました。これは他の分野では見られないことでした。
司会:話しを戻しますが、当初の目的の中で、「国内外問わず宗門に関するさまざまな情報を提供する」とか「相互の情報交換を目指す」というものがありまして、とても20年前に目的に掲げたものとは思えないぐらい現在に適合するものだと思います。どうしてこのような目的が立てられたのでしょうか?
晴山:当時、海外では「禅」ブームがおきていることが分かっていました。ではブームに乗って海外の人が取れるアクションを考えた時、まず海外のお寺を紹介してあげればいいんじゃないかと考えました。そしてその次に英語のテキストの掲載を考えました。
司会:「相互の情報交換を目指す」という点についてはどうですか?
晴山:手作り感が満載のHPでしたが、あえて自分たちで仕組みを理解し、自分たちで運営が出来るようにして、問合せのメールも自分たちに来るようにしていました。それは、メールで指摘されたことをすぐにHPに反映できる体制をつくっておきたかったからです。メールには、ほぼ100%返信していたはずです。
司会:それは現在でも続けていますね。
●開設時のインターネット事情
司会:パソコン通信の時代にこれだけのことが出来たというのは、すごいと思います。
大森:とにかく当時のインターネット事情というと、「ウィンドウズ95」の普及は一番大きかったと思います。ウィンドウズ95が出てから、なぜインターネットが広まったかというと、それより前の時代のMS-DOSとかウィンドウズ3.1の場合は、接続するためのソフト、電話をかけるソフト、接続するソフト、ウェブを閲覧するソフト、そしてメールを見るためのソフト、という数種類のソフトを、一般的には雑誌とかCDとかを買って手に入れるしかなかった。それが全部一括でウィンドウズ95には入っていたということが一番革新的なことで、それが出来たのでインターネットの需要が広まったのだと思います。
晴山:これに比例して、通信回線がどんどん早くなっていきます。いまから考えると全然ですが、ISDNが出来た時には、すごいなと感じたものです。
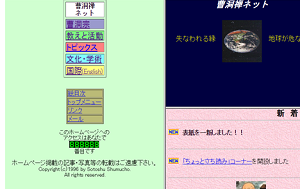
●アンケートによるユーザーのニーズ調査ついて
晴山:当時、教化施策「グリーンプラン」の一環でストラップをつくったと思いますが、それを、アクセスカウンターの切りの良い節目の番号の人にプレゼントするということをやったことがあります。
司会:最近またプレゼント企画を始めました。2か月に1回くらい実施しています。アンケートを兼ねて多くの方にご意見をいただています。
晴山:アンケートといえば、当時も回答者へ先着で何人かにプレゼントを差し上げたこともありました。
大森:中間報告も掲載した憶えがあります。
晴山:このアンケート調査をもとに宗務庁に需要を示して、「こんな資料をアップしてほしい」という一般の人の要望を伝えていました。
司会:ユーザーが求めていることに出来るだけ対応してあげることが大切ですね。
大森:当時は「何がトレンドか?」ということも全然分からない時代でした。今だと普通に新聞やインターネットで見れば分かることが、全然分からない時代でした。そのためにアンケートは基礎資料になり大切でした。
●初期のコンテンツについて
司会:ここに一番最初のHPの資料がありますが、かなりの量の記事を上げられています。8月から会議が始まって、12月にはオープンされている。短い間にどのようにしてこんなにたくさんのコンテンツが出来上がったのでしょうか。
晴山:いきなり新しいものを求めることは出来ないので、既存の教化資料や出版物から、使用許可を得られたものを片っ端から掲載しました。すでにOCRで文字を取り込むことも出来たので、スキャンして、誤字脱字だけチェックして流し込んでいました。
司会:当時のコンテンツ、例えば「供養について」では、お仏壇の祀り方や法事の営み方を掲載していますが、今でも大人気のページです。現在でも遜色ない内容です。
曹洞宗のHPは、他の宗派とくらべるとボリュームがある方ですが、当初から出せるものは全部出していこうという姿勢があったということですね。
大森:全曹青のHP開設前に、他教団のHPを色々リサーチしていました。禅宗では臨済宗のある寺院がやっているHPを参考にしましたが、そこは「坐禅会のあるお寺」という情報を掲載していました。それを見て、まずは坐禅会だろうなと思いました。曹洞禅ネットでは「認可参禅道場」の寺院情報を掲載しましたが、その意味はやっぱり大きかったです。
晴山:また、評判が良かったのは「精進料理」ですね。
大森:精進料理は非常に良かったですね。
●宗務庁からの情報発信、メール対応について
司会:HPが軌道に乗ってからは、重要だったのが相互の情報交換としてのメール対応ですね。メール対応は、相互の情報交換という意味で大変重要なサービスです。例えば仏事のことからプライバシーに係るものまで、様ざまなメールが寄せられますが、対応にご苦労されたと思います。
晴山:その頃は、「お寺の跡継ぎがいないから何とかならんか」というようなものもありました。あとは、地域差の激しいもの、例えばお布施の額とか法要のやり方についてのメールがかなりありました。
大森:昔から「お布施」にまつわる話が多くありました。後は住職の資質に関わる質問が多かったと思います。
晴山:メール対応は最初からずっとやってきましたが、たぶん一件一件の丁寧な回答が信頼につながったのではないかと、そのように思っています。
●トップページの変遷・機能の追加
司会:ホームページの画面にも大きな変遷があったと思います。
1万5千の寺院を検索できる「寺院検索」機能が追加されたり、坐禅会開催寺院、梅花講開催寺院など、様ざまな情報が追加されてきました。そういったものを作ったご苦労をお聞かせ願えますか。
大森:機能を追加するという面で、当時われわれ担当者がこだわっていた部分が3つあります。それは、「出版物の販売」と「寺院検索」と「申請用紙のダウンロード」です。
寺院検索は課題も多く、常にお寺の情報がさらされることによって、各寺院から批判が出ないかといったことを議論した記憶があります。経緯としては、他のサイトですでにどんどんネット上に寺院の電話番号から住所までが出ている状態になっていたので、それだったらきちんとこちらで情報を出さないといけないのではないか、ということで始まりました。
晴山:寺院検索は、一回出してしまえば良いと思っていたのですが、「平成の大合併」が始まって、すごい量のデータ修正がありました。
大森:毎年すさまじい状態でした。
晴山:「申請用紙ダウンロード」は、僧侶用のパスワードを設けて、一般の人は入れないようにしようという部分も出来てきましたね。
あとは、「文献検索」は最初からできていました。文献検索は宗学研究部門が中心となり、毎年新しい論文など、刊行されたものを追加して使ってました。
大森:つい先日、学者の人から言われたのですけれど、曹洞宗関連の出版物を大本山永平寺の機関紙『傘松』まで検索できるのは、これしかないので、非常に大切にしてほしい。しかし、最近更新が止まっているので、非常に残念だ、とおっしゃっていました。
晴山:駒澤大学の仏教学部の学生たちが卒業論文を書く時やゼミでも、曹洞宗のことならここで調べなさいといって、使わせています。しかし、どんどん扱いが小さくなって、入口が分かりにくくなっていますね。ちょっと学生たちに指導しにくくて。以前はトップページの下部にバナーがあったと思いますが。

大森:HP全体の流れからいうと2003年からデザインもちゃんと検討しようということになりました。WEBデザイナーで宗侶の広瀬知哲師によって、デザインの見直しが始まった後には各段にデザイン力があがっています。
晴山:どんどんとプロらしい仕組みになってきています。
(次回・後編へつづく)



