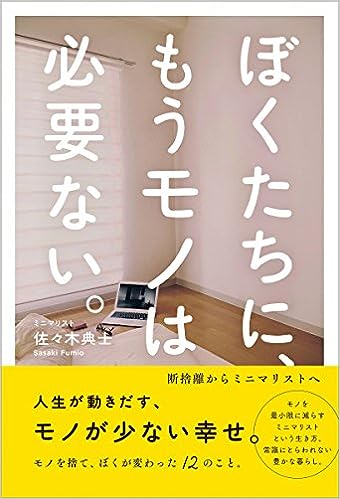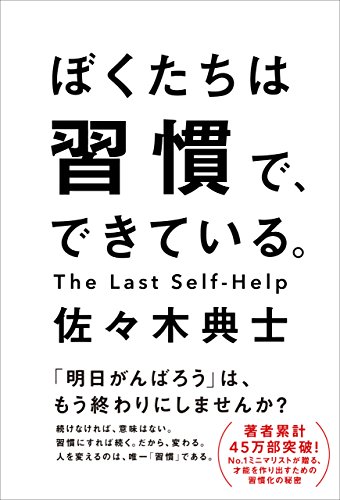「ミニマリストと禅僧との対話」(1)~曹洞宗の坐禅を体験
ミニマリストの佐々木典士さんが、大本山永平寺別院長谷寺専門僧堂を訪ねてくれました!

左から佐々木典士さん、宇野全智師、乾郁雄師
ミニマリストとは、持ち物をできるだけ減らし、必要最小限の物だけで暮らす人のこと。佐々木さんは、不要なモノを手放すことで本当に大切なものに焦点を当て、そこから見える幸せの本質について、『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』という著書にまとめられています。また、「習慣」をテーマとした、『ぼくたちは習慣で、できている。』を出版されており、どちらの書籍も曹洞宗との親和性が感じられる内容となっています。著書に禅や仏教の教えが出てくることもあり、お話をお聞きしたいと取材のお願いをしたところ、「取材よりもどなたか禅僧の方とお話してみたいです」という、ありがたいお返事をいただきました。
2023年7月6日(木)、長谷寺専門僧堂において曹洞宗総合研究センター常任研究員の宇野全智師と曹洞宗宗務庁文書課長の乾郁雄師との対談を行いましたので、これから数回に分けて記事をお届けいたします。
佐々木典士さん初の著作『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』は26カ国語へ翻訳、世界累計で80万部突破。習慣についての著書『ぼくたちは習慣で、できている。』は12カ国語へ翻訳されている。
佐々木さんのプロフィールはこちら
■修行道場を案内
対談の前に、僧堂(坐禅堂ともいう。)、東司(=トイレ)、浴司(=お風呂)の三黙道場を中心に寺院内をご案内いたしました。三黙道場とは、私語が禁止された三つの場所という意味です。

僧堂では、それぞれの僧侶に自分が坐禅をする場所が割り当てられ、基本的にそこで寝起きすることとなります(道場によって異なります)。坐禅をする場所を単といい、その前側の板の部分を牀縁と呼びます。単には函櫃と呼ばれる開閉式の棚があり、上の段に修行生活の必需品、下の段に布団をしまいます。
起きて半畳寝て一畳という言葉がありますが、修行僧の生活はまさにその通り。寝るときは一畳に布団を敷いて就寝し、起床の合図によって函櫃に布団をしまいます。洗面などの身支度を済ませたら、単の半畳を使って朝の坐禅が始まります。坐禅後は、本堂で朝の読経を行い、その後、僧堂の単に戻り坐禅を組み朝食です。
牀縁は、食事の際に使う応量器という食器を置く場所となりますので、手や足をついてはならない決まりとなっています。応量器を使った食事作法はなかなかに難しく、覚えるまでに時間を要する人も少なくありません。食事は皆で食べて皆で終えることになっているため、ご飯を食べるのが速くなってしまう僧侶もいます。
曹洞宗では、日常生活のすべてが修行であり、洗面、食事、トイレ、入浴等、それぞれに日常生活を修行にするための偈文という短いお経が決まっていて、一つひとつの行いを疎かにせず、大切な修行として丁寧に勤めます。三黙道場では私語が禁じられていますが、誰も見ていない場所でも心の緩みに気を配り、自分自身を調える時間とするのです。
修行道場の一日の流れや、どのようなことを行っているかを説明した後、毎日坐禅や瞑想をされている佐々木さんに、曹洞宗の坐禅を体験していただきました。

■曹洞宗の坐禅を体験して
宇野 先ほど曹洞宗の坐禅を体験していただきましたがいかがでしたか?
佐々木 気持ち良かったですね。自宅ではすぐに坐り始めることが多かったのですが、あのような準備運動や深呼吸するのも良いなと思いました。
宇野 準備運動で行った肩の上げ下げや首を回すというのは坐禅の作法書にはないもので、仲間と考えたオリジナルなのですが、初めに大きく息を吸って息を吐いてというのは作法書に書いてあります。深呼吸は坐禅をするに当たって心と身体のこわばりを取るために行うもので、とても大事な作法です。また、振り子のように体を左右に揺らす左右揺振という作法は、動の状態からゆっくり静の状態へ繋げていく感じを大切にしています。左右揺振は、坐禅の前と後で手の置き方が異なりますが、動から静へ、静から動へ、左右への体の振れと合わせて閉じに向かう、開くに向かうという、その感覚も大切だと思っています。
佐々木 手の置き方は、この法界定印という形が正式なのですか。
宇野 曹洞宗ではそうですね。宗派によって違いがあります。
佐々木 面白かったです。坐禅中は、「この後何を話すのかな」とか考えちゃいました。
宇野 坐禅会などでは、無理に考えないようにしようとせずに、考えたものは流してくださいとお伝えするのですが、「なかなか流せない」とおっしゃる人も多いですね。「そういうときは、なかなか流せないな~って流してください」と言ったりするのですが。
佐々木 瞑想するときは、まぶたが重くなるというか、情報が入ってこないようにするのが良いのかなと思っていたのですが、そういう感じでもないんですね。
宇野 眠りに入るような瞑想もすごく気持ちいいなと思うときもありますし、僕もそういうやり方のヨガを教わったことがありますが、曹洞宗の坐禅は情報や感覚をシャットアウトする方向ではなく開かれた感じで、聞こえるものは聞こえたままにします。
佐々木 坐禅中に目を閉じないという作法もその表れなのでしょうね。
宇野 そうですね。外界から切り離されていくというよりも、外界との境目がなくなっていくような感じでしょうか。そういえば、「アースデイ東京」というイベントに参加されたことがあるとお聞きしています。
佐々木 はい、行ったことがあります。
宇野 僕は実行委員の一人として関わっているのですが、野外ステージのすぐ横に、曹洞宗のブースを出していす坐禅体験をやったりしてるんですよ。
佐々木 結構うるさいですよね。
宇野 音量は無茶苦茶です。ロックバントなどがガンガンとやっているのですごい音がしますが、それを流せるようになると、ただ自分を素通りしていくだけなので、「ロックだな~」という感じで坐っています。
佐々木 なるほど、それは新しい発見です。その場にある柱や植物になるみたいなイメージだと上手くいくのかなと思っていたのですが、それはちょっと違うんですね。
宇野 自分が鳥かごになってそこにある。それをすべてが風のように通りぬけていくようなイメージです。
佐々木 宇野さんの本に出ていた「ザル」のようなイメージですね。
宇野 そうですね。ザルも鳥かごも、水や風を留めず、また入ってくるのを拒まないように。外界との境界がなくなって、いろいろなものが素通りしていくことが心地良いという感じです。
佐々木 僕がいつもやっているのは、睡眠の一歩手前みたいな感じだったなと思いました。
宇野 瞑想にも色々なやり方があり、好みもあるとは思いますが、今日一緒に体験して頂いた曹洞宗の坐禅も、また機会を見つけて試して頂けたら嬉しいです。
佐々木 ありがとうございます。勉強になりました。

次回から、ミニマリズム、習慣、仏教、禅について話が始まります。