【人権フォーラム】曹洞宗教区人権学習の振り返りと障害理解の学びと行動について
1.これまでの人権学習(障害理解)の取り組みについて
障害理解と行動形成の研修
初めまして、NPO法人風雷社中理事長の中村和利と申します。2020年度曹洞宗人権啓発資料作成委員会の委員を拝命し、この原稿を執筆させていただいております。
わたしは障害のある人たちが「地域で障害のない他の人と同じ生活をしていく」ための福祉サービス(居宅介護・移動支援・相談支援)と、「障害理解と障害者差別解消」を促す為の学習・研修活動や啓発活動に取り組む活動をしています。啓発活動の一環として、「アースデイ東京」に「ガイドヘルパーから始めようキャンペーン」として参加してきた中で、曹洞宗(アース禅堂)の方々と知り合い、連携をしていく機会をいただきました。
障害者支援のNPO法人と宗教教団である曹洞宗が「地球のことを考える日・アースデイ東京」で出会い、障害者差別解消に取り組む流れができたことは、多様性を包摂した社会や組織を作っていく取り組みとして、とても意味のある事だと思います。

曹洞宗の人権擁護推進主事研修会では、障害平等研修(DET研修)の実施にコーディネーターとして関わりました。障害平等研修とは障害当事者がファシリテーターとなり研修受講者へ視覚教材と対話を通して「障害はなに? 障害はどこにあるの?」を自ら考え、環境の中にある障壁(=障害)を解消していく為の具体的な行動を自ら形成するものです。この障害平等研修でのポイントは下記のものとして考えています。
・障害(ディスアビリティ)は、個々の機能障害を示すものではなく、機能障害と環境の関係の
中に生じるものである。障害を生じさせている環境を改善していくことで、障害を解消していくことが求められている。
・障害を解消するために必要な環境整備や合理的配慮の提供は、障害のある人に「特別なこと」を提供するのではなく、環境整備や合理的配慮の提供があり、障害のある人が、障害のない人と平等な状況になる。
この視点を獲得するプロセスとして下記のポイントが重要となります。
・知識として教えられることは個人の中に定着しづらく、自らの気付きが重要。
・「気付き」で終わるのではなく、気付きに基づく自身の具体的な行動(実際に取り組める内容)をすることにより、視点を自身の中に定着させていく
・障害のある人との対話が気付きや行動形成の軸となることで、障害当事者への共感や多様な視点の受容を促す。
指導的な役割を担う人権擁護推進主事に障害平等研修を通し、障害の社会モデル視点の獲得、行動形成の研修を障害当事者との対話を経験してもらうことから始まりました。
2.学びのポイント
障害のある人と共に考える
2019年度教区人権学習資料について振り返りたいと思います。障害のある人たちと「お寺訪問」を実施した様子と、その後に開催された障害のある人たちと僧侶による座談会を題材として構成されています。そのまとめの中で、3つの学びが記されています。
①出会うことで「障害」を理解する
お寺訪問は、一方的な「お寺のバリアフリーチェック」ではなく、障害のある人と受け入れる側のお寺=僧侶が、訪問を通して「なにが障害」となるのか?(なっているのか?)を一緒に体験し、どのような工夫や配慮が必要かを共に考えていく場面を伝えることを意図としました。一方的に机上の理論として「障害者」への配慮を受け入れ側が考え、用意するのではなく、障害のある人と一緒に体験をして、その人にとって何が必要かを共に考え、環境の中にある障害の解消に一緒に取り組むことの重要性を伝えたいと思っていたのです。
②「障害」は共通の課題
「障害当事者」と言うことがあります。「障害は環境の中にある」としたときに「障害当事者」とはなにを指すでしょうか。一般に「環境の中にある障害によって不当な不利益を負わされている機能障害のある人」だと考えています。しかし「障害」と言う事象の前での「当事者」は「不当な不利益を負わされている機能障害のある人」だけではありません。環境を作る人たち、変えていける人たち、そのすべてが「障害」という事象に対して「当事者」であるのです。
「障害」によって機能障害がある人たちが寺院を訪れない、訪れることが出来ないことでの不利益は、機能障害のある人たちだけではなく、その人たちと出会う機会を「障害」によって奪われ、多様性の欠如した状況の中に居つづけなくてはならない人たちにも生じているのではないでしょうか?
多様性が包摂された状況こそが、人の営みを豊かで寛容なものとしていけると考えます。
③対話によって「障害」を解消する
「障害」の解消において、障害のある人との対話の必要性を重要なものであると考えています。機能障害の状況も、その人個人の経験や背景も個々で異なることから、環境整備や合理的配慮の提供のあり方は多岐に渡るからです。また、「してあげる」「してもらう」と言った一方通行な関係は、障害のある人、障害のない人の分断を強化する側面があります。
障害のある人と対話を大切にして、環境の中にある障壁=障害に共に向き合う関係性の構築が大切になります。また、対話を通し課題と向き合っていく体験は、他の課題と向き合っていく力を高めてくれると思っています。
3.学びのポイント
見える障害と見えない障害
「障害は環境の中にある」とした学びの中で、多くの人の着目点は物理的なものに向きがちになります。知的・発達障害、精神障害等の機能障害のある人への環境整備や合理的配慮の提供は、多くの場面で置き去りにされています。
世界中の人たちを苦しめているCOVID-19の感染防止として「マスクの着用」が新しい生活様式となってきていますが、感覚過敏がある知的障害、発達障害のある人たちにとって「マスクの着用」が困難な場合があります。実際、わたしの関わる知的障害のある人が「マスクの着用」ができない為に、公共施設入館の際に、係員から「マスクの着用」を指示され、着用ができないと困ると言った無理解を示されたケースがあります。施設の入館に関するガイドラインがマスクの着用を必須にしてしまっていたのです。
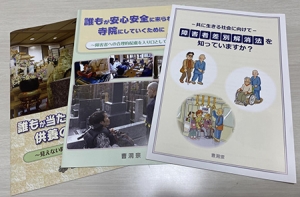
このような状況に対して厚生労働省から「マスク等の着用が困難な状態にある発達障害のある方等への理解について」という表明がHPに挙げられています。この中で世界保健機関(WHO)の「Q&A:COVID-19に関連する子どもとマスク」から「発達上の障害、その他の障害、またはその他の特定の健康状態のあるあらゆる年齢の子どもにマスクを使用することは必須ではなく、子どもの親、保護者、教育者、医療提供者、またはそのいずれかによってケースバイケースで評価されるべきである。いずれの場合でも、マスクを容認することが困難な重度の認知障害または呼吸障害のある子どもは、マスクを着用する必要はない。」と言った引用が紹介されています。このような「見えない障害」への周知や理解のシェアは大切なものであると考えます。
2020年度教区人権学習資料「誰もが当たり前にお参りできる供養の場を目指して~見えない障害のある人の視点から~」は冊子と視聴覚映像(DVD)が作製されました。
この資料では「差別心はどこからくるのか」として大阪私立大学・池上知子教授からの寄稿を掲載しています。この中で人間は自己肯定が強くあり、同時に自身の所属する集団(カテゴリー)を他の集団よりも優位な存在としようとするものであることが記されています。そこから生まれる差別心は自覚が難しい強固なものであることが示されました。
しかし、その解決の方法として社会心理学の知見から「拡張接触理論」が提唱されました。これまで差別解消のアプローチとして他の集団との直接接触が奨励されてきたが、自身の所属する集団の中の身近な人が、他の集団の人たちと接触している様子を知ることでも集団の垣根を融解することができるというものです。
この提言に基づき、僧侶が精神障害当事者自助グループや知的障害者グループホームを取材し、報告していく内容としました。取材先も単純に障害のある方々の入所施設や病院などではなく、地域の中で普通に暮らす精神障害のある人たちが同じ障害があるがゆえに理解しあい活動する自助グループや、知的障害のある人同士が結婚し育児をすることを支えるグループホームとしました。障害のない人たちと同じ「人間」であることを伝えられる内容を目指しました。
また、DVDでは、葬儀場面での精神障害のある人への差別的事例を題材にし、精神障害当事者と僧侶の対話形式の教材としました。
学びのポイントは次になると考えています。
・障壁=障害は物理的な環境の中だけではなく、障害のある人を排除して育まれてきた社会規範や慣習などの中にもある。
・心理的安寧を求める人間の根源的な部分に基づく差別心を軽減させていくためには、間接接触理論でのアプローチが新たな取り組みとして重要である。
4、障害理解と障害者差別について
ここで「障害者差別解消都民アクション2021」をご紹介します。「障害者差別解消都民アクション」は曹洞宗でも数多く実施させていただいてきた、障害平等研修の体験と周知を通して障害者差別解消の取り組みを東京都民に広めることを目的に、2019年、2020年に実施し、2021年は「障害平等研修」と2019年度に採用した「精神障害のある人の視点からの障害の社会モデル研修」の2つの障害者差別解消の為の取り組みの紹介と体験を実施します。
今回のアクションではプレイベントとして動画配信サイトYouTubeでの座談会の配信も行いました。【障害者差別解消都民アクションon line座談会 その2「精神障害当事者の視点からデザインした『障害の社会モデル研修』について」】では、精神障害当事者の山田悠平さんと曹洞宗僧侶である宇野全智さん(曹洞宗総合研究センター専任研究員)、本多 清寛さん(曹洞宗宗務庁人権擁護推進本部)の対話を配信しています。https://youtube.com/playlist?list=PLgEnT9-bEZPaZmlqT-HQ6̠_DSOaIc8uzaL
5、おわりに
地球環境のことを考える「アースデイ東京」での出会いから、曹洞宗での障害理解推進に関り、障害者差別解消の為のイベントに曹洞宗僧侶に参画していただく、このような多様で柔軟な取り組みこそが、日本社会の多様性の包摂を進めていくのではないかと思っています。自らのカテゴリーに留まらず、多様な価値観に触れ、協働し、そしてその体験を自らの所属する集団の中でシェアしていくこの繰り返しに希望を感じています。
障害者差別解消のための取り組みについて、ご質問やご感想、ご提案のある方は下記メールにお問い合わせください。
jinken@sotozen.jp
●ご案内
「障害者差別解消都民アクション2021」は3月20日(土)14時から開催されます。関心のある方は是非、ご参加ください。申し込みなどの詳細は、下記リンク先HPにて近日ご案内致します。
(DETサポーター大田HP https://www.det-ota.org/)



